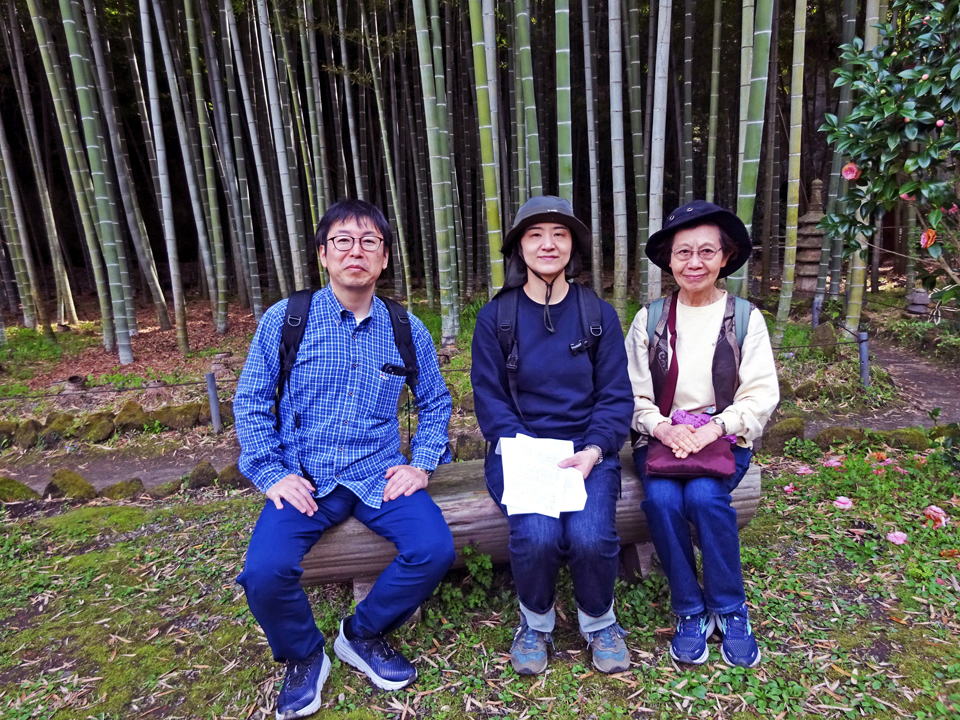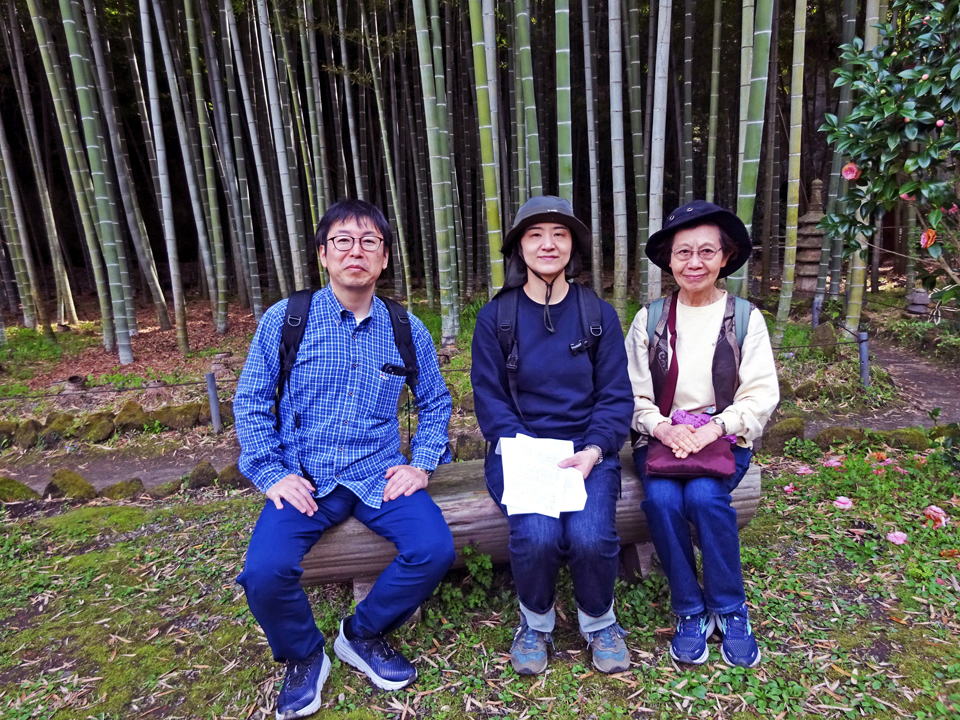| 英勝寺 |
英勝寺 (えいしょうじ)
1636年に創建された英勝寺の境内には、創建当時から現存する建物が数多く残っている。主要な建物である山門、仏殿、鐘楼、祠堂、祠堂門(唐門)は、すべて国の重要文化財に指定されています。浄土宗のこの寺は、かって水戸徳川家につながる尼寺で、太田道灌の居館の地であったといわれています。今は鎌倉唯一の尼寺で、尼寺に相応しい佇まいを見せている寺です。家康に寵愛されたお勝の方は、太田道灌の曾孫・康資の娘です。幼名をお梶といい、やがて家康の側室の一人になります。家康の死後、お勝の方は出家し英勝院と号しました。将軍・家光から寺地として賜り、寛永11年(1634)、菩提寺としたのが始まりです。英勝尼が、この地を先祖である道灌の屋敷跡と考えた為といわれています。寛永13年(1636)、寺が完成すると英勝寺と名付け、徳川頼房の娘・小良姫を玉峰清因と号し、開山としました。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
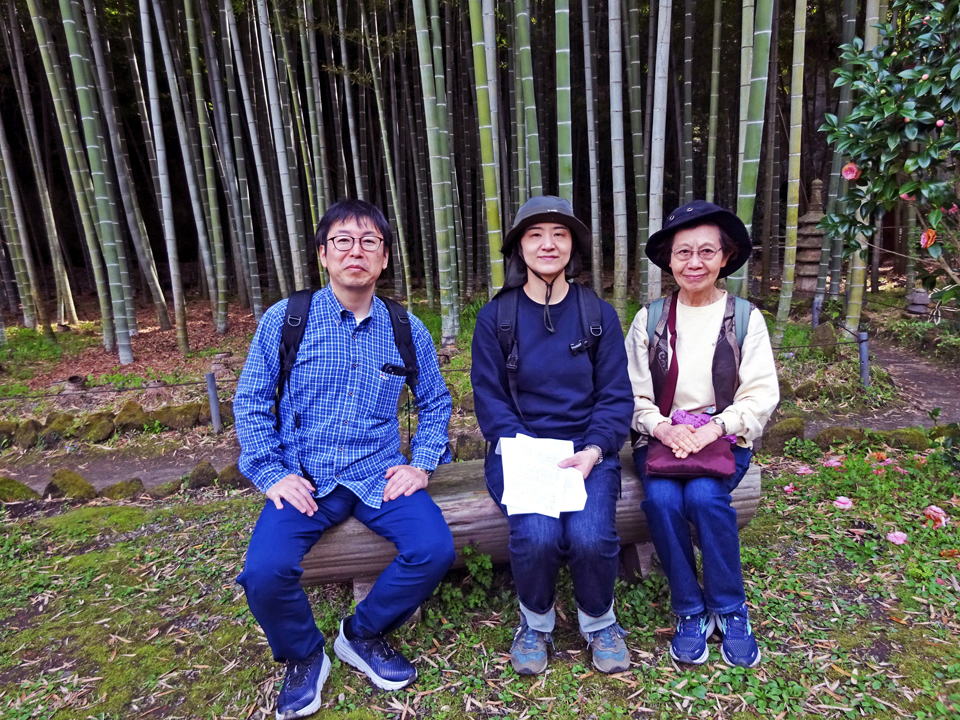 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 鎌倉永勝寺の境内にある岩窟をくり抜いたトンネル状の構造と、内部に刻まれた仏像については、「闇から光へ」「俗世から悟りの世界」を象徴していると言われています。地中や岩窟は静寂であり俗世から隔絶されているため、瞑想や修行に適した空間とされて来ました。また、通路内に仏像が刻まれていることは、通路内で、仏と出会えこころを整えて祈り、悪霊や災いから身を護るとされています。複数の仏像が刻まれている場合、それは曼荼羅(まんだら)的な宇宙観に触れることも表わしています。仏教では「生死(しょうじ)」のサイクルを越えて涅槃(ねはん)に至ることが目標です。岩窟トンネルをくぐり抜け、仏像と向き合うという行為は、この輪廻からの「解脱(げだつ)」の象徴とも捉えられているのです。 |
|
 |
太田道灌公の墓
江戸城築城で有名な太田道灌資長はこの地で生まれ扇谷上杉家の家宰として、活躍しました。その曾孫である太田康資の娘梶(のちに勝)は、德川家康の側室として水戸德川家の初代頼房の養母となり、德川家を支えました。彼女は、出家後に英勝院と号し、3代将軍德川家光より、鎌倉源氏山一帯を賜って英勝寺を開山しました。この太田道灌公の墓は、文政九年(1826)に、水戸德川家の子孫である英勝寺住職が以前の墓を再建したものです。 |
|